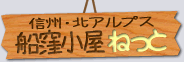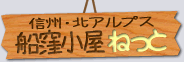| |
 |
10月30日
小屋閉めから2週間あまり、瞬く間に過ぎてしまいました。船窪便り、すっかりご無沙汰しています。
毎年恒例となっております、下の廊下山行は10月16,17日と10月23,24日の2回催行されました。第一回目総勢16名にて無事終了することが出来ました。
私は10月18日、かねてより行きそびれていた槍ヶ岳へ登ってきました。こゝに2泊3日の山行記録をご披露いたします。
朝に夕に船窪小屋から眺めている槍ヶ岳。高瀬渓谷を前景に雄々しくそびえている槍、表銀座の東鎌尾根、北鎌尾根は高瀬渓谷かた槍に向かい、西鎌尾根は美しい曲線を描いて、槍の穂先を支えている。南にそびえる穂高連峰を従者のように従えて、槍は紺碧の空を背景にそびえている。
まだ若い20代のころ、烏帽子〜三俣蓮華〜双六〜槍と歩くことがあったが天気が悪くなり、千丈沢一気に下山したことがある。それ以来、穂高から燕からと何回となく機会はあったのに遂に槍ヶ岳へ登ることを逸してしまっていた。今年こそはと願っていたらそれが叶う日が来た。
「10月中なら同行してもいいですよ」とK氏。それではと決めて、夫の了解を得た。「えっ、お母さん、槍ヶ岳に登ったことないの?・・・」と言われる度に悔しかったけれど、”やっといけるぞー”と小屋閉めの頃からルンルンだ。天気が心配だが16,17,18日は晴れマーク。登るときに雨さえなければと出発を決めた。
燕から縦走したかったけれど、台風で天気は長続きしないようだ。それにしても、今シーズン程、台風に悩まされた年は無かった。船窪小屋のお客様もそうだった。8月までは何とか昨年以上においでいただいたが、9月になり天気予報の悪さに客足はパッタリとなってしまったものだ。表銀座縦走は天気次第ということになり、上高地から一気に槍沢を登ることにした。
栂池発5:00、松本駅西口まで夫に送ってもらい、6:35発島々行に乗る。島々線は空いていて、登山者の姿はほとんど見当たらない。島々にてバスに乗り継ぎ上高地着7:30分。20年以上ご無沙汰している間に、上高地はすっかり様変わりしている。公衆トイレに入り100円のチップを入れる。休む間もなくすたすた歩き出す。私は10K弱の荷物だ。夫は”もう少し軽くした方がいいぞ”と言ったが、初雪に覆われた稜線を見ての出発だったので、衣類が冬支度になってしまった。
上高地はシーズンオフなのにさすが人が多い、月曜日でも行きかう人は途絶えることがない。
横尾山荘に11:00着。昼食にラーメンを注文し、持参のおにぎりを食べる、ラーメンどんぶりは小さめで船窪小屋の2/3ほどの大きさである。この時私は持参した握り飯を2人で食べたので、この時点でご飯類はなくなってしまい、他は非常食のパン類だけとなったことは大きな誤算だった。
横尾山荘は新しく立派で、新築中の建物も後方にある。涸沢への橋もグリーンのきれいな橋脚の上に立派に造られていた。上高地から要した時間は3時間。コースタイム通りだという。槍ヶ岳山荘に電話を入れ、今晩の宿の予約をし出発する。
澄み切った梓川の清流、時々岩魚の影が見え隠れする。12時丁度に歩き出したので夕方5時には槍ヶ岳山荘に到着できるという。時々台風で倒れたのか、大木の倒木が痛々しい。緩やかなのぼりの道を限りなく歩く。横尾山荘から上高地まで11KM。横尾から槍ヶ岳山荘まで11KMとあった。こういう道を歩いていると、つい急ぎ足となってしまう故か、足の裏が痛くなってきた。一の俣を過ぎ、二の俣を過ぎた頃から急に岩の登り道となる。登っているのは私とK氏だけ。下りの5パーティーに会う。槍沢ロッジ2時頃着。これからはどんどんきつい登りとなる。土の道でなく、石の大きな岩の登り道なので、足の裏が痛い。この道を3時間登るのは参るなあ、と思いながら、黙々と歩く。K氏は私の後からゆっくりついてくる。すでに重い食料等は預けてあるので、彼の荷物は相当重くなっていると思う。「槍沢?ありやあ長いでね。登るなんてことしなんで下りましょ」と言った松原氏の言葉をしきりに思い出しながら”この分じゃ5時到着は無理かもしれない”と心の中で思った。休むたびにパンや非常食を食べたが、握り飯が無いのが痛手だった。私はパンで間に合っていたが、K氏は飯類が欲しかったに違いない。槍ヶ岳は三角錐の山頂をツンと稜線上に乗せたかのように聳えている。その左手の肩に、槍ヶ岳山荘が大きく乗っている。窓にはすでに灯りがついて、私を呼んでいるかのようだ。
だんだんきつくなる斜度、それに加えて岩稜の道となれば、もっとも体力を使い、足に負担がかかる道である。”こりゃ、七倉尾根なんかへの合羽だなあ。第一、距離が長すぎるなあ”なぞ、ブツブツ言いながらヘエヘエしながら登っていく。
そんな私を見てKしはリュックを全部担いでくれると言う。「そうだね、わたし次第だからね。暗くなっても困るし、お願いするか」と涸れの申し出に応じさせてもらう。だんだんきつくなる斜面、ごろごろ岩、2年前に登ったネパールヒマラヤのカラパタールを連想した。カラパタールとは”黒い岩の峯”という意味らしい。
槍ヶ岳山荘の建物は稜線上にあり、窓には灯りがともっている。あそこに山荘が無ければこの情景はまさにヒマラヤのカラパタール峯そのものに見えた。特にこの岩の道こそは・・・・。
幡隆窟をすぎ、少し登ると殺生ヒュッテとの分岐点である。
ベランダへ出て私達を見ている人がいる。”この時間なら、ここへ泊まった方がいいぞ”といっているかのようだ。このヒュッテには栂池で隣家のO家の次男坊健君が小屋番をしているのだ。このまま殺生ヒュッテへ行ってしまおうと思った。しかし槍ヶ岳山荘に予約してしまったので、頑張って登らねばとあえぎつつ登る。K氏も相当バテたようだ。
もうすでに5時をすぎ左肩には月が昇っていた。月明りだけでも歩けるほどの明るさである。憧れの槍ヶ岳、頭上に聳える三角錐の槍を見ていると船窪小屋から眺望する槍ヶ岳の方がずっと立派に見えると思う。
北アルプスの”王者槍ヶ岳”を望むには、やはり七倉尾根が船窪小屋が絶好のポイントであると改めて認識した次第である。
槍ヶ岳山荘へはPM5:40着。実に上高地を出てから10時間を要した行程であった。夕食はすでに用意されており、山口支配人は不在だったが、ビールやワインのサービスと共に手厚いもてなしを受けさせてもらった。
10/19霧のち雨
次の朝は濃霧だった。昨夜眺めた槍ヶ岳は霧の中、登頂をあきらめ飛騨を下ることにした。霧はすぐに雨となり、合羽上下ををつけての下山となった。この下山道がまたまた長い長い行程だった。
初めて歩いた奥飛騨の道、新穂高温泉上尾高原に着いたのはPM3:00.槍ヶ岳山荘を出てから8時間の下山だった。
そして新穂高ロープウェーは思いがけぬ急斜面にあった。冬でも行けるという新穂高ロープウェー。栂池や八方の方が、ずっとずっと緩やかで平坦なゲレンデの中の駅舎である。ここは特に年間稼動の管理は厳しいだろうなあと思いながら、雨の中、合羽着用のままバスに乗り込み、栃尾温泉の民宿栃尾荘(笠が岳ヒュッテ経営、立派な民宿)にて宿泊させてもらい、次の朝、安房トンネルを越えて、松本発10時半スーパーあずさにて白馬着、11時15分。
3日間の槍ヶ岳山行は無事完了しました。
-次は下の廊下山行を掲載させてもらいます。-
|
|
|
|